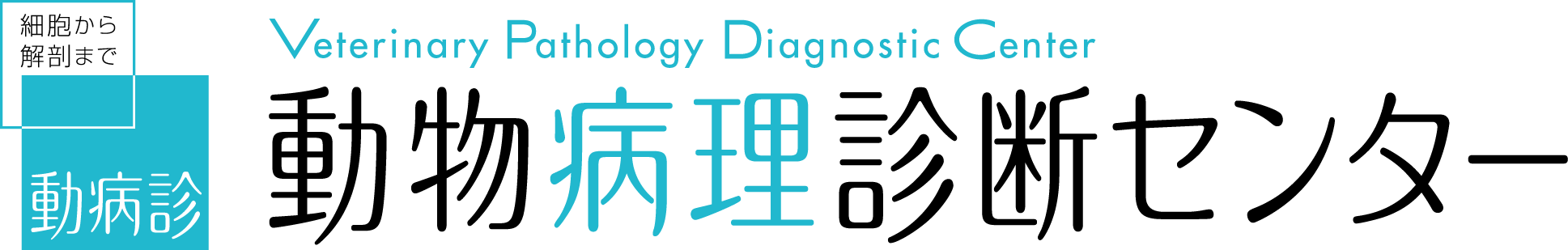形態学的骨髄検査セット Comprehensive morphologic bone marrow evaluation
骨髄塗抹と骨髄コア生検の両方に対する形態学検査を行います。末梢血塗抹とCBCデータも同時に提出してください。すべてのデータを包括的に判定いたします。(輸血をした場合は必ず依頼書にその旨を書いてください)
細胞診スライドは、気化したホルマリンにほんのわずかでも暴露すると染色性が変化して検査ができなくなります。細胞診スライド(骨髄塗抹・末梢血塗抹)と、ホルマリン固定材料であるコア生検のサンプルは、必ず別々の袋にいれ、袋を密閉してから提出してください。袋は2重にし、輸送中でもホルマリンの影響が起きないようにしてください。ホルマリンは細胞診スライドの近くでは絶対に扱わないようにしましょう。
骨髄塗抹と骨髄コア生検の違いって何?
通常、細胞診は病理組織検査の前段階の検査のように考えられていますが、骨髄検査では細胞診と病理組織検査の意義は全く違っています。
骨髄細胞診は、細胞1つ1つの形態学的観察に優れていますので、個々の細胞の分類、分化の程度の観察、ME比判定などを行います。
骨髄コア生検の場合は、骨髄の構造を見ることに優れています。骨髄全体の細胞占有率や巨核球の数の判定を比較的客観的に行うことができます。また細胞診では診断が困難な骨髄線維症の確定診断をすることも可能です。一方で細胞1つ1つの分類には不向きで、正確なME比率判定はできません。骨髄コア生検は、骨髄の様子を全体的に捉えることに適しているといえるでしょう。
このように、骨髄細胞診と骨髄コア生検では役割が異なっており、そこで得られた情報は相互に補完しあうものです。骨髄や造血の状態を総合的に判断するためには、骨髄細胞診とコア生検の両方を行うのが望ましく、さらに末梢血の情報やCBCのデータ、そして臨床情報などを総合的に判断するのが一番良い方法であるといえるでしょう。
もし、骨髄細胞診とコア生検のどちらか1つしか選べないのであれば、骨髄細胞診を選ぶ方が、得られる情報量が多いので第一選択とします。骨髄を何度吸引しても骨髄が得られない’dry tap'の場合は、骨髄線維症が鑑別診断となりますので、コア生検をお勧めします。
コア生検が得られた場合、生検材料から細胞診塗抹標本を得ることができます。コア生検材料を、先の細い針などでスライド上で軽く転がします。この作業はコア生検の診断性を損なわないように素早く済ませます。骨髄コア生検は、採取後5分以内に固定をするようにしてください(気化ホルマリンには十分気を付けてください。)