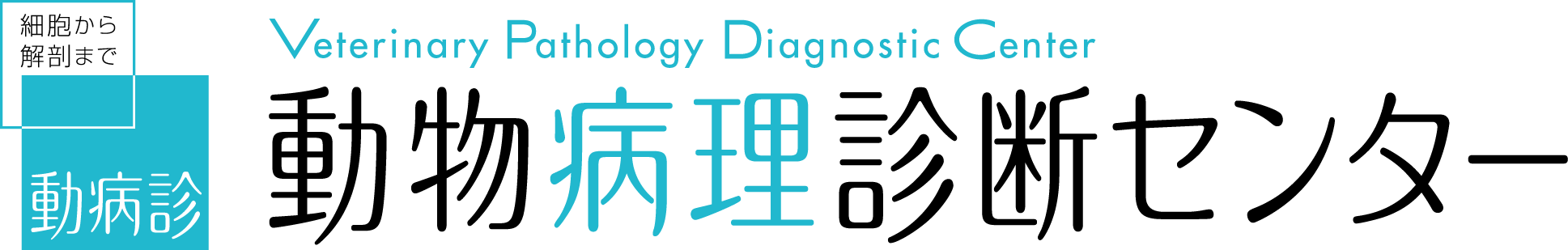なぜ病理解剖を行うのか?
病理解剖という選択肢を、全国の臨床獣医師に
現在、本格的な病理解剖を行う施設は、獣医大学とごく一部の病理検査会社に限られています。私たちは、その状況を変え、すべての臨床獣医師が、必要に応じて「病理解剖」という検査が依頼できるようなシステムを作りたいと考えています。
病理解剖は、訴訟に関わる可能性のある場合以外にも、生前に臨床の検査で説明がつかなかった症例の原因を究明したり、治療の効果があったかどうかを確認したり、稀な症例を最期までみとどけるなど、多くの学ぶ場を与えてくれます。もちろん、理由もなく入院中や手術中に突然亡くなったり、ワクチン接種後に亡くなった場合などには、必要に応じて第3者に公正な目で評価してもらうという面も、病理解剖の大切な役割です。
*********
ある獣医師の飼っている犬が、原因不明の白血球増多症と消化器の症状に悩まされていました。その獣医師から、白血球増多の原因として、慢性好中球性白血病の可能性はないかという相談を受けましたが、慢性好中球性白血病は診断が難しく、あらゆる白血球増多症の可能性を除去しなくてはならないこと、また消化器の症状があるので、まずはそちらの原因を探されてはどうか、とお答えし、慢性好中球性白血病の参考文献をお伝えしました。ところが、内視鏡検査と生検のスケジュールを組んでいる最中に、その犬は急性腎不全となり亡くなりました。
臨床症状の原因が知りたかったその獣医師は、ご自分で剖検をされ、組織診断を私たちに依頼しました。そして組織検査で、その犬が消化器型のリンパ腫であることが判明し、白血球の増多は2次的なものであるということが分かりました。
*********
「病理解剖の依頼は日本ではほとんどありませんよ」
私たちが、病理解剖の業務を始める準備段階で、多くのこのような声が聞かれました。日本は、遺体に対して特に敬意を払い、尊厳をもって扱う国です。さらに、近年ペットと飼い主の距離が縮まって家族同様になっており、遺体にメスを入れるのを良く思わない感情が多くあることは理解できるところです。
また、このような声も聞かれました。
「病理解剖では、ビジネスは成立しない」
これは、ある意味本当のことです。病理解剖は、主に肉眼検査である解剖と顕微鏡を使った組織検査に分かれています。肉眼検査ですべての臓器を調べるのに数時間はかかりますし、全組織から臓器を採取し、組織スライドを作り、顕微鏡で詳細に観察しますと、その準備時間と検査時間は膨大なものになります。さらに、検査をする診断医には肉眼、組織、追加検査の結果をすべてを総合して臨床情報と照らし合わせ、最終的に死の原因を説明する知識と能力が求められます。こうして費やされる多くの時間と能力に費用をそのまま反映させますと、膨大な金額になってしまいます。獣医先進国であるアメリカでも、病理解剖の多くは大学や公立の検査組織で行われています。私設の検査機関で病理解剖を扱うところがごくわずかです。やはり、多くの時間と費用が必要な病理解剖がビジネスとして成り立つのは難しいのです。
それでも、私たちは病理解剖という検査を提供しようと考えています。
それは、日本でも病理解剖の重要性を広く認知してもらい、臨床獣医師や飼い主が望めば、病理解剖を受けることができるシステムが必要であると考えるからです。
細胞診断から病理解剖まで、形態病理検査を一貫して提供することで、私たちは日本の獣医学の発展に貢献したいと願っています。